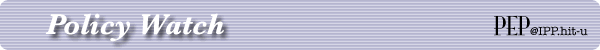
|
| No. 2009-002 |
医療政策:「予防」にかかる期待一橋大学 国際・公共政策大学院 公共経済プログラム 田中秀明 人は誰しも、自らが健康でいられることに大きな価値を感じる。それはとりわけ、病気や怪我の状態に陥って、それまで当たり前であった健康が損なわれたときに強く認識するものである。けれどもそれにもかかわらず、一旦健康を取り戻した後は、再び訪れる日々の暮らしの中でいつしか不摂生な行動へと流れてしまい、自分自身で少しずつ疾病リスクを高めるような選択を重ねてしまうという心理構造もまた、多くの人が理解できる部分ではないだろうか。 食事・運動という生活習慣を念頭におくとき、そこには当然、「好きなものを食べたい」、あるいは「家の中でゆっくりしたい」といった個人の効用を高めるという理由から、偏食や運動不足という不健康な生活習慣を選択してしまうという面がある。しかし重要なことは、そうした選択の前提として、少々の不摂生をしたところでそう簡単には健康は損なわれないはずであるというリスク認識が存在していることである。 自らの欲に逆らって健康的な食事・運動習慣を実践することは、個人に対して若干のストレスを生むかもしれず、また時間というコスト(機会費用)を課すかもしれない。しかしそれは将来において健康を獲得するための自らへの投資である。その投資効果が不確実であることを理由に個人が投資を合理的に抑制した場合、過少投資に起因して発生しうる疾病の治療コストを誰が負担することになるだろうか。それは我が国においては公的医療保険ということになる。その意味で、健康への投資水準を個人の裁量に委ねたことによって、あらかじめ防ぐことが可能であったかもしれない疾病リスクが公の負担として顕在化する事態に対しては、政府として予防政策を推進することの妥当性が存在するものといえる。 我が国で現在最も注目を集めている予防政策は、2008年にスタートした特定健康診査・特定保健指導(メタボ健診)であるといっていいだろう。この制度は我が国で近年急増している糖尿病に対する対策として、予備軍に対する生活習慣改善から始まり、生活習慣病の有病者に対する医療を通じた重症化予防までを、段階的かつシームレスに行うことを目指すものである。 現在、糖尿病患者およそ800万人のうち、半分の400万人が非通院者となっている現状がある。同時に、増え続ける患者数に対して専門医の不足も進行している。よって、単純に通院率を引き上げるのみでは、糖尿病の予防・治療環境の質を低下させることにもなりかねない。そこで、低リスク者に対する一次予防はかかりつけ医が担当し、高リスク者は専門医が重症化の食い止めを行うという機能分化を明確にすることで、広範な予備軍・有病者全体に対して効率的な予防を実施していくことを意図している。 一般に用いられる「予防」の概念は比較的広いものであり、性質によって以下のような一次予防~三次予防という類型化がなされている。したがって、「予防」を議論する際には対象となる予防の性質を明確にする必要があり、これ以後は主に生活習慣改善を通じた予防を念頭に置いて話を進める。  日本人の食事や運動の習慣や意識について、厚生労働省が調査したデータがある。図1では運動の習慣があるかどうかを尋ねた結果を示している。  個人の運動習慣を改善・推進するために何らかの政策的介入が行われる可能性を想定するとき、その効果についてこのデータは何を示唆するだろうか。左端の水色で示された「十分に習慣化している」と答えているグループを除いたおよそ7割の人々が、まずは介入効果が期待される対象者であるといえる。その中でも本人が既に持っている意欲を後押しすることで運動習慣の改善が比較的実現しやすいと思われるのは、「実行しているが、まだ習慣化していない」グループ、次いで「実行しようとしているが、十分に実行できていない」グループであり、合計すると男性で約30%、女性で約35%存在している。 一方、「実行していないが、実行しようと考えている」グループ、さらには「実行していないし、実行しようとも考えていない」グループに関しては、運動しないことが習慣化しているグループであり、外からの介入によって簡単なきっかけを与えられるだけでは習慣の改善を期待しにくいものと予想される。 介入政策とは、これら右側にある貧しい生活習慣のグループを一つずつより良い左のグループへと移行させる役割を果たす。行動科学の領域では、こうした各グループを段階的に変化するものと捉え、健康問題に対して個人が理解や関心を深めることによって行動変容が起こるものと考える。そこでは、各段階に対応した適切な介入の方法・強度を選択することが重要であると考えられている。 次の図2においては、食習慣を改善するために必要と考えていることを尋ねたデータを示している。ここからは、政策的な生活習慣への介入のあり方を考える上で、それに対する人々のニーズがどのような部分に存在するのかという示唆が得られる。  回答の中で、男女とも最も大きな要素として挙げているのは「時間的なゆとり」であり、将来の健康に対する望ましい健康行動の実践が時間的な面から制約を受けていることがわかる。注目されるのは「学校での教育」、そして「保健所、保健センター等、行政からの情報提供」という回答であり、いずれも個人が健康のための望ましい食事習慣に関する理解の促進や、生活の中で実践するための方法論を身につけることなどが重要であると考えることを示す。 しかし、ここで「食習慣改善のために必要なこと」として考慮されるべき欠落した要素があるといえる。それは自らの疾病リスクとの関係という面である。仮に理想的な生活習慣のあり方を十分に理解していたとしても、それを実践しなかった場合に自分の健康が脅かされるという認識がないために、そうした生活習慣を実践できないという構造があることは冒頭で述べた通りである。したがって、健康行動をとることの便益を自分自身の問題として認識するための介入として、個人の健康状態に関する情報(検診結果など)のフィードバックや、専門的な医師や看護師によって現状から予測される疾病リスクに関する適切な説明の実施などが重要となってくる。 現時点で健康な個人が、生活習慣が原因で将来起こるかもしれない(そして起こらないかもしれない)何らかの疾病に対して現実的な危機意識を持つことが難しいことは事実でもある。十分に健康な個人にとって、健康への過剰な投資はむしろ無駄になりかねないという面もあるだろう。それでは、人は自分自身が実際に特定の健康リスクにさらされている状況に直面したとき、どのような健康行動をとるのだろうか。 筆者は2008~09年にかけて実施した研究において、特定の治療環境(注5)に置かれた患者群が治療(薬剤)の副作用として発生する骨粗鬆症のリスクに直面した下で、どのような生活習慣の改善を実践するかという患者行動に関する調査を行った(注6) 。そこでの調査結果は、患者群の特殊性の問題や調査方法が十分に厳密ではないことなど、解釈に一定の留保は必要であるものの、患者の健康行動のあり方や望ましい介入方法を考える上での示唆を与えうるものと考えており、以下で要点を概説したい。 はじめに、この研究における「予防」の内容と性質に関して説明する必要がある。予防介入の目的は、食事・運動という生活習慣の改善を通じて薬剤副作用としての骨密度低下を防止することであり、介入の方法として、骨粗鬆症リスクと生活習慣に関する情報提供と指導を看護師が実施するとともに、現状の生活習慣水準についての自己評価を2時点において実施するというものである。ここでの「予防」は、生活習慣を通じて骨粗鬆症への罹患をあらかじめ防ぐという面で基本的には一次予防という性質として捉えられるが、特定の薬剤副作用における骨密度低下リスクにさらされたハイリスク者であるという面からは、半ば顕在化したリスクに対する重症化予防(三次予防)としての側面も併せ持つものと考えられる。 調査結果から最も注目される点は、「(副作用を持つ)薬剤の服用年数が増すにつれて、骨粗鬆症への関心と健康行動への実践度がともに低下する」という傾向が見られたことである。このことは、服用開始とともに直面する骨粗鬆症リスクに対して当初は十分な認識を持ちながらも、服用期間の経過とともにリスクの発現しない状態(注7)が持続するにつれて、その不確実性に関するリスク認識を下方修正していく過程が存在していることが推察される。しかしながら、服用期間中(注8)は高リスク状態が継続すること、また生活習慣のレベルが健康状態のアウトカムに与える影響の不確実性などを考慮するならば、そうした「予防コンプライアンス」の低下ともいえる自己調整行動は必ずしも合理的な意思決定とはいえない可能性がある。そうした面から、有効な予防の実践に関してケアレベルで示唆されることは、服用当初時点でリスクに関する十分な情報提供を行うとともに、長期服用者が予防を継続するための適切な生活カウンセリングも重要になるものといえる。 調査結果におけるその他の論点として、「介入前からより望ましい生活習慣水準にある患者群ほど、介入を通じた実践度が高い」という傾向も観察された。このことは、情報提供を中心とした今回のような軽度の予防介入においては、個人が既に持っていた意欲を後押しする効果が中心であり、当初から低い行動水準の患者群に対する改善効果は十分に大きくなかったことを表している。介入の強度と患者行動との間の関係のあり方は、予防介入の有効性・便益性を評価する際の重要な要素になるものといえる。 社会保障財政が膨張を続ける中で、cost savingという期待のもとに予防政策が打ち出されている側面が多分にある。けれども、そこに予防効果に関する十分な予測の裏付けがあるわけではなく、予防の有効性を事後的に計測することがどこまで可能であるのかも疑問である。そこには無論、そもそも予防がもつ不確実性の問題があり、とりわけ生活習慣領域においては各個人のコミットメントの可否に決定的に依存する面もある。 政策面、ケア面いずれについても、生活習慣への予防介入における高い有効性を実現するためには、患者行動の分析を通じて介入方法の継続的な改善を続けていくプロセスが基本となるべきであると考える。その意味で、動機は何であれ、政策レベルで予防という観点が注目され、実施に移されていることそのものは歓迎すべきことである。政府が社会保障政策を担うことの意味を考えるとき、予防政策が本来持つはずの国民一人一人の生活の質(QOL)を引き上げるという役割に立ち返ったうえで、cost benefitという観点から予防政策のあり方を議論していくことこそが、公共政策の目指すべき方向であると考える。
|
